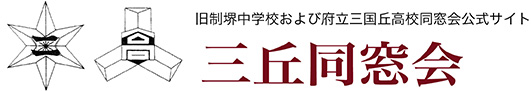権代美重子さん(高20回)の「江戸の食商い」 法政大学出版局から出版
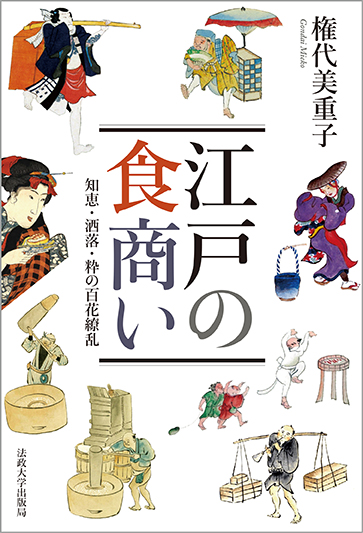
昨年2月17日の第16回アカシアトークカフェで講師を務めていただいた権代美重子さんだが、前著書「日本のお弁当文化」に次いで、本年6月に「江戸の食商い――知恵・洒落・粋の百花繚乱」が出版された。<第1章 江戸のまちと人々の暮らし>から<第13章 高級料理茶屋「八百善」の繁栄>まで平易な文章と豊富なカラー図版に加え、14編のコラムからなる労作。
【江戸時代に一変した食の豊富さ】
もし、醤油・砂糖・味醂・かつお出汁のような調味料がなければ、日々の食卓はどんなに無味乾燥なものになるだろうか。これらの調味料は江戸時代の中頃から安く入手できるようになり普及した。醤油は享保年間になって銚子・野田で醸造されるようになり「地廻り醤油」と呼ばれ、現在も千葉県にある醤油の主要なメーカーの発祥となった。独自の製糖法が確立された砂糖は、文化文政期に国産品がそれまで高価だった輸入品の量を上回るようになった。これらの調味料は味覚の充実だけではなく、保存効果があることから食生活を豊かにするためには欠かせないものになっている。
【大火が多かった江戸】
当時世界有数の大都市であった江戸は火災が頻繁に起こり、特に江戸の大半を焼き尽くした明暦の大火(1657年)の後の復興のために職人や人夫が江戸に移り住み、享保6(1721)年頃には男性:女性の人口比が18:10だったという。さらに単身赴任の武士が約50万人も居たことから食事を提供する店や居酒屋が繁盛した。現代の外食産業の走りと言ってもいいだろう。
【水茶屋の看板娘】
江戸時代も半ばになると、現代のカフェのようにお茶を楽しめる店「水茶屋」がたくさんでき、「茶を五、六十杯飲んで手を握り」という川柳も読まれた。水茶屋の看板娘に近寄るために何度も店に通う姿は、現代のCDを何枚も買ってアイドルと握手してもらう姿と似ているようでほほ笑ましくもある。
現代のチラシ広告にあたる「引き札(ひきふだ)」も商品やサービスの宣伝のために配布されるようになり、さまざまな料理本すら発行されている。奇抜な装束や大道芸で客寄せをすることもあった。
さらには、100円ショップに似た商売まで考案され、まさに現代のビジネスの源流とも言えよう。
【イメージが途切れずに理解できる】
権代さんの文章は「日本の弁当文化」の時もそうであったように、懇切丁寧で分かりやすい。知らない人が居るかも知れない、あるいは使われ方があやふやな言葉は説明を付けてある。(たとえば「オカラ」「夜鷹」「南蛮」「彼岸」のような語)そのために定義が明確で、イメージが途切れずに読み進めることができる。14編のコラムと精細なカラー図版や写真が説明を補ってあまりある。
「専門的な裏付けをきちんとしながら誰にもわかりやすく楽しく読める本」を心がけた姿勢のたまものと言えよう。
【聞きかじりの豆知識から正確な情報へ】
この本を読んでいると「あ、そうだったんだ」「なるほど!」と感じることが少なくない。
1日に2食だったのが3食になった/マグロのトロは捨てられたり肥料にされた/土用の丑(うし)の日に鰻(うなぎ)を食べるのは平賀源内が広めた/「すし」はなぜ「寿司・鮨」と書くか/蒲焼の語源……のような聞きかじりの豆知識がなぜそうだったのかとさらに理解を深めることができる。
【膨大な資料ときれいなカラー図版】
江戸の大火・関東大震災・東京大空襲などの惨禍を潜り抜けてなおかつ豊富な書物や図絵が残されていることに驚かされる。江戸の人達の文化意識の高さを知ることができる。
権代さんが今回この本を出版するにあたっては、膨大な文献や資料にあたり、精査した時間と労力は大変なものであっただろうと容易に推測できる。貴重な資料を基に、江戸の庶民の生活を鮮明に再現し身近に引き寄せてくれている。
自然災害・流行り病・飢饉・幕府の取り締まりなど江戸の庶民の暮らしは必ずしも楽なものではなかったはず。そんななかでも、江戸の人々は「粋」と「したたかさ」を忘れずに、遊び心を持ったたくましさが、現代の豊かさの源になったことを感じる。
【身近に感じられる江戸の生活】
同書のテーマは「食の商い」ではあるが、食にまつわる江戸の文化や生活全般についての研究の成果と言える。この本を読んでいると、江戸時代の人々の生き生きとした暮らしぶりに引き込まれ、日本食を味わうときには、今までとは一味違った楽しみ方ができそうだ。テレビドラマの時代劇の見方すら変わってタイムスリップさせてくれる気がする。
書名=「江戸の食商い――知恵・洒落・粋の百花繚乱」
発行所=法政大学出版局
サイズ=四六判
定価=本体2500円+税
権代美重子(ごんだい みえこ)さん
日本女子大学卒業、立教大学大学院修了。日本航空(株)国際線客室乗務員・文化事業部講師を経て、ヒューマン・エデュケーション・サービス設立。1997年より(財)日本交通公社嘱託講師、国土交通省・観光庁・自治体の観光振興アドバイザーや委員を務める。2009年より横浜商科大学、文教大学、高崎経済大学の兼任講師(ホスピタリティ論、アーバンツーリズム、ライカビリティの心理と実践、他)。