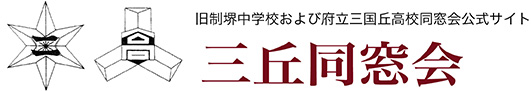「拝啓われらが先生!」第8回・南英世先生

恩師を訪ねるこのコーナー。第8回は社会科の南英世先生です。18年間にわたって高41回から高58回の現代社会や政治経済などで、そして教員生活の終盤に半年間、高77回の公共(2022年度からの必修科目)で、三国丘高校の教壇に立たれました。同窓会でも度々話題になる、個性派教師の南先生。果たして、どんな半生を歩んで来られたのでしょうか。
挫折・挫折の人生
石川県羽咋市出身で、金沢大学経済学科に進学。当時「大学では火炎瓶が飛び交い、寮は学生運動の巣窟」だったとか。講義はマルクス経済学ばかり。そこで学生の同好会である「ケインズ研究会」に入って、本格的に近代経済学を学んだ。人生最初の挫折が就職活動だった。念願の日本銀行の最終面接まで残るものの、あと一歩で大魚を逃す。失意の中、恩師に声を掛けられ、金沢大学で助手となる。しかし8年ほどでスパッと辞めてしまう。「大学は自分が住む世界ではない。仮にこの世界に残っても一流にはなれない。どうせ一度きりの人生、せめて一流半ぐらいの人生を送りたい」、そんな思いになったのだ。そのときすでに31歳。
三国丘高校での18年間
大学を辞めて大阪に出たのは、妻・正子さんの出身地であり、目標として視野に入っていた教員の採用が40歳までだったから。しばらく民間のシンクタンクに勤めた後、20倍以上の採用試験を勝ち抜き、ようやく三つ目の職業として教員という天職を得る。そして2校目に赴任したのが三国丘高校だった。 「三国の生徒となると ほとんどは僕より賢い生徒ばかりですからね。受験参考書を頼りに教えても、生徒は誰も聞いてくれません。夜中の2時3時まで 勉強に明け暮れました」と当時を振り返る。みんなを面食らわせた小論文テスト
南先生の名物と言えば、一問100点の小論文テスト。「アダム・スミス、マルクス、ケインズについて論ぜよ」「日本の財政赤字について論ぜよ」「20世紀とは如何なる時代であったか」というようなテストに、中学校まで一般的な記述式や、記号の選択式のテストしか経験してこなかった高校一年生は、まず面食らう。年度始めに株の銘柄を選ばせて「年度末に値上がりしていたら加点」したり、当時ではまだ珍しいディベートを取り入れた授業だったり、教科書通りではない授業が次々展開される。
「難しい言葉でごちゃごちゃ言っても、それでは本当に分かったことにならない。小学生にでも分かるように説明できて、初めて分かったということ。そのためには、書かせるのが一番」、「枝葉末節にこだわる授業はやらない。物事の本質を問う授業をやりたい」、「政治経済の教科書1冊で大事なことって4つしかないんです。憲法、集団安全保障体制、有効需要の原理、比較生産消費説。この4つが分かれば、世の中の動きは分かります。あとはどうでもいいことなんです」、南先生はそう力説する。コンピューター採点など、効率化が進む日本の教育現場に対しても「本質を考えさせることをやらない」と憂いていた。
定年になった後、趣味の囲碁に打ち込み、7段の免状と関西棋院の公認囲碁インストラクターの資格を取得。週に一度、碁会所の席主をしながら、3歳から90歳の生徒にボランティアで囲碁を教えている。「やっぱり褒めて育てる。これはもう何の世界でも一緒だなって。やる気にさせる。やる気にさせたら、教員の仕事はおしまい」。
My life is a big success
教えることへの情熱は以前と変わらない。外国人もよく来るので、その経験から「囲碁を打つ人のための英会話の本」も書いた。現在は、囲碁教師、囲碁ライター、執筆活動と「三足のわらじ」で忙しい毎日を送っている。2月には世界で初めて行われた「国際障害者囲碁大会」の取材にソウルまで出向き、4月には4冊目の著書として『よくわかる経済学入門』という本を角川ソフィア文庫から出版した。
「遊びに集中できる人は、仕事にも集中できる」と語り、自身を「My life is a big success」と評する南先生は、今まさに第二の人生を謳歌している。
〔聞き手=渕上猛志(高48回)、小池稔(高34回)〕
(2025.6.2)
(2025.6.2)