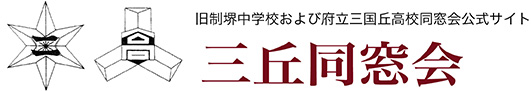第18回三丘アカシアトークカフェ
横田順一朗さん(高21回)/─生命維持の仕組みから考える─救命救急の技

第18回三丘アカシアトークカフェは2024年12月7日に開催された。講師は医師になって47年、そのキャリアのほとんどを救急医療に携わってきたという横田順一朗さん(高21回)、テーマは「─生命維持の仕組みから考える─救命救急の技」。
横田さんはわが国救急医療のパイオニアであり、その著書は救急医療のバイブルになっている。だがご本人は「全然えらくないんです。高校時代も運動は苦手だったし、FLD(語学部)に入ってて…演劇部にも端役でちょっと入ったりしましたが。大学(大阪大学医学部)に入ってから、これではいかんと合気道を始めました。ただし、他流試合をやるんですが、近大のような強いところとはやりたくない、帝塚山やったらええよという感じで(笑)」。
そんな横田さんだが「卒業後、外科、麻酔科を経て早々と救急医療を選んだらおもしろくて、以来ずっと救急医療ひと筋に歩んできた」そうだ。「今日は救急のエッセンスをわかりやすくお話しします」ということでお話が始まった。
「蘇生」は太古の昔からの願い
スライドで加熱法、ふいご法、逆さ吊り法(溺死のケースで使用)、樽転がし法(同)、雪の中に埋める、馬に乗せて馬を早足で歩かせる等、名前を聞いただけで驚くような図が示される。近代以前に行われていた「蘇生法」だ。
太古の昔から、人間は人を「蘇生させたい」「なんとか救いたい」という欲望を持っていたのだ。ふいごを使って口に空気を送り込む「ふいご法」は16世紀から300年間にわたって使用されたという。「現在の心肺蘇生法」として胸骨圧迫のイラストが出てきた時はほっとした。
救命救急の技 第一部 ─生命維持の仕組みから考える─
さて「生命維持の仕組み」だ。肝臓、肺、腎臓、心臓、脳、子宮といった臓器や骨(背骨、骨盤、ろっ骨)や手がスライドに示されている。「この中で命にかかわりそうなものを5つ、少なくとも3つ、(各自の手元にあらかじめ配られた)付箋に書いてください」と横田さん。うーん、あれとこれと…あとはなんだったかな…考えながら書き込む参加者たち。「私たちの体は50兆くらいの─だれが数えたか知りませんが─細胞でできている。生きていくにはこの細胞がすべて生きていないといけない。細胞が生きていくには何が必要か。そこでアデノシン三リン酸(ATP)。これは細胞の生命維持に不可欠で、エネルギーの通貨とも言われている。そしてエネルギーのもとは栄養素と酸素なんです」
「栄養素と酸素、どちらも体の外にしかない。私たちはこれを取り込まないといけない。さて、栄養素と酸素、どちらがが枯渇しやすいか? 酸素です。断食をする人がいるように、栄養をとらなくても、そう簡単に死なないけど、酸素はそうはいかない」
酸素を取り込むのに必要な臓器は肺、心臓、脳。それぞれの役割があり、この3つが輪っかになってぐるぐるまわっている。

「どれが一番大事か? 順番はあってないようなもの。三つのうち、脳みそ=中枢神経というのは自分はなにもせず命令する、えらそうな、殿様みたいなもんですね。しかも血液や酸素をたくさん使う。低血糖にも弱い。でも、中枢神経が命を支えているんです。あと、もうひとつ。人間は恒温動物です。なので体温管理も大事」
「この生命維持の仕組みのうち、どこが悪いのかをチェックする。これが救命医療。治療するには順番がある。知識があってもそれだけではなく、テクニックが必要になる」
「怪我をして救急で運ばれてきた人の9割は出血で亡くなる。まず出血を止めないといけない。しかし、『予定手術』と違って、どこで出血しているのかわからない。そういうときはとにかく、『ここから血が出ているであろうところ』をまず止める。そしてICUへ。その後、再手術。これを繰り返す。ダメージコントロールサージェリーというものです。戦艦大和が沈んだのはこの概念がなかったからと言われる。ダメージコントロールオフィサーがいれば、少なくとも大和は沈むことは避けられたのではないかと」
救命救急の技 第二部 ─時・空への挑戦─
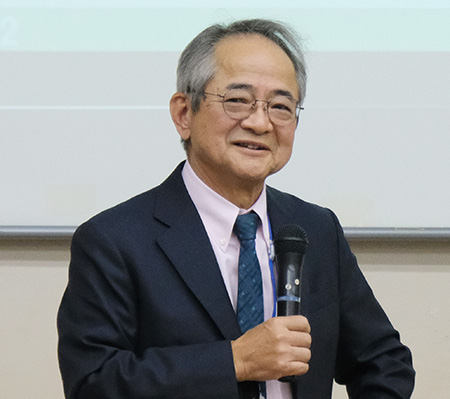
休憩をはさんで、第二部。
「時(time)」と「空(space)」の制約。救急医療では、これをどう克服するかが問題だ。
「医師は病院や診療所にいるが、人はそんなものと遠く離れたところで急変したりする。時間的余裕のある診療と違って、患者の自主性で病院を選択できない。どこへ連れていけばいいのか。これは深刻で、かつ放置できない問題です。何か制度的な仕組みをつくらないといけない」
「今までの話は病院に医師がいて、患者が来て、という1対1の関係での話。救急医療はちがう。広く、地域でみるとあちこちで急変している人がいて、医療機関もそこそこあるが、医療アクセスにつながっていない。テクニックを持っていても展開できない。これをどうやって克服するかが救急医療の命題。
餅を詰めた程度では現場で何とかなるかもしれないが、それ以上は無理。どんなに離れていても、病院でないと対応できない。運ぶ時間を短くしないといけない。ドクターヘリ、あるいは医師を現場に連れていく…。救急救命士という制度もできているが、日本ではまだまだ限られた範囲の処置しかできない」
「地域で救急医療をやっていくのなら『鳥の目』で見てシステム化を考えなければならない、研究は『虫の目』でもいいけど──私の亡くなった後輩が言ってました」
縦割り行政の問題点
救急車は総務省消防庁の管轄で、その費用は自治体が出している。消防法、消防組織法のもとで動いている。医療職である救急救命士も。だが、病院に入ると、そこは厚労省の担当。医療法や医師法で管理される世界。
「患者が一人発生する。救急車で運ばれる。病院で治療を受ける。この短い時間の間に2つの組織体が動いている。その費用、財源がまったく違うところから出ている。縦割りです。いい制度をつくろうにもこれが壁になっている。そこで、10数年前から、こうした行政の枠を超えて両者を取り持つための協議会をつくって調整をしています。『メディカルコントロール協議会』です。時間(time)も、距離(space)も少しでも縮めたい、と」
横田さんは現在、堺市の、そして全国のメディカルコントロール協議会の代表を務めておられるそうだ。なんと心強い!
質問その他
質問者「救急車の利用を有料にしようという動きがあるとか。どう思われますか?」
横田「最近の救急要請で多いのが、高齢・独居などで移動の足がないからというもの。民間救急車、病院救急車を使っていこうという考えがあるんですが、財源の問題でなかなか議論が進まないんです」
質問者「救急車に3回乗りましたが、もうちょっと、どないかならんかな。振動がひどくて…あと、私の経験から、人脈が大事だと思ってます。どこの病院がどうとか、いろんな情報が必要なので」
質問者「堺だとベトナム人とか、最近は外国人の方が増えていますが、こういった人たちへの対応は?」
横田「言語の問題ですね。観光客、特に単独観光客の場合も困ることがある。ただし、救急の場合は、体から発する生命兆候のサインにより判断する。むしろ一般診療の場合の方が困ることが多い」
最後に、高一のとき横田さんと同級生だったという女性からは「今日は楽しく帰れます。縦割り行政の問題点を打破しようと頑張っている。いろんなことを立体的に学ばせてもらいました。まだまだ死ぬまで頑張ってほしい」とエールが。横田さんも笑いながら「ありがとうございます」と応じた。
今回はリモート参加者2人を含め55人の参加者があった。
最後は恒例の記念撮影。せーの、はい!

(2024.12.14)