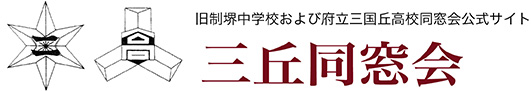陶芸教室「あなたも土の虜(とりこ)」開催

今回は午前の部・午後の部の2回、定員はそれぞれ10人に抑えての実施。3時間で「1 紐を1本ずつ積み重ねる」「2 ろくろ回し」「3 高台づくり」までの工程に挑戦する。さて、無事に作品ができるだろうか?
なお、ろくろや道具、土(信楽の土だそうだ)は人数分が用意され、参加者が各自用意したのはエプロンだけ。各自の席にはろくろ台や様々な道具、土をこねたものがあらかじめ用意されている(下の写真は作業途中の状態。最初に撮るのを忘れました)。

まず土をこねて丸めたものを平たくする。これをろくろ台に載せて竹串のような道具を当て、えいっと回すと円形に切り取ることができる。これが底になるので、ここで器の大きさが決まる。

この上に、ひも状に伸ばした土を積み上げていく。親指を上手に使って押さえつつ。 この方法で湯呑みでも壺でも皿でもなんでもできるという、基本となるものだ。

指の腹で押し下げるようにならしながら、積み上げたひも状の土の境目が見えないようにする。これを何回か繰り返し、好みの高さにする。皆さん、すっかり夢中。隣の人が自分より進んでいると急にあせったり。

次にいよいよ、ろくろを使って滑らかにする。濡らした鹿皮で水分を補いながら。厚みもここで調整する。納得いくまで何度でも。

そのままでは波打っていた縁の部分も余分なところを切り取る。この時も道具をあてがって、ろくろを回すと一瞬で。そしてその後、またろくろを使いながらなめらかに仕上げていく。どんどん形が整っていく。ろくろって、なんて素晴らしい道具なんだ。
だいたいできたところでドライヤーの風をあて、ある程度乾いたら下の方を斜めに削り、高台を作る。好みのサイン(イラストでも良い)を彫り込んで、ひとまず完了。
思うようにいかず苦労する人もいたが、「初めてなら当たり前。私も最初はなかなかできなくて悔しい思いをしました」と久山さん。芸術の道は険しいのだ。



同じ土を、同じ量使っていてもそれぞれの個性が自然に現れるのが面白く、また不思議なところ。しかし、皆さん、なかなかお上手じゃないですか?
体験教室はここまで。作った器はこの後、釉薬をかけて焼き、完成した状態で届く予定だ。その日が待ち遠しい!