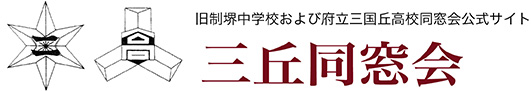2025年総会ゲスト講演 高橋朋宏さん(高35回)/「世界的ヒットはこうして生まれた」 〔抄録〕
全世界で1500万部を売り上げたベストセラー「人生がときめく片づけの魔法」(サンマーク出版)の生みの親で、現在は(株)ブックオリティ代表として活躍するタカトモさんこと高橋朋宏さん。2025年総会では売れる本を作ってきた編集者としての思い、近藤麻理恵さんとの出会い、その本がベストセラーに上り詰めていく様子をつぶさに語っていただきました。
人は変われる
(プロジェクタに映し出された、およそ片づけとは縁のなさそうなデスク)
この美しいデスク。何を隠そう僕のデスク(笑)。「人生がときめく片づけの魔法」の編集者の僕。おかしいですよね(爆笑)
僕はめちゃくちゃ片づけが苦手でした。おそらく僕のデスクは出版業界ワースト5に間違いなく入ってた。自信あります。
そんな僕がこんまりさんと出会って片づけの本を作ることになった。発売間近に「これじゃやばいな」と(笑)。まずいですよね。で、直前に、週末、会社に来て「片づけまつり」を実行しました。こんまりさんにも自腹で6万円払ってレッスン受けて。そして、こうなりました(みごとに片づけられ、すっきりしたデスク、「おーっ」と歓声)
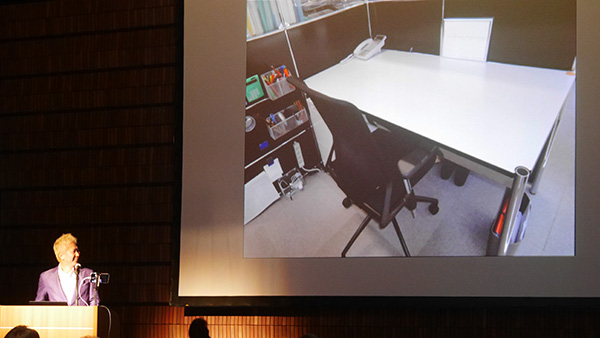
ここで拍手が起きなきゃいけないんです。(拍手)
週末に片づけをやって、月曜日、僕の不在中にデスクを見た部下たち「高橋さん、会社やめるのか…」。みんな思ったそうです。ほかのフロアからも、社長も僕のデスクを見に来たそうです。それくらい会社に衝撃が走った。(笑)
それまでも毎年年末には整理して、年始は片づいた状態だったんですが、2月、3月になると元の木阿弥になっていた。
人は変われるんですね。(爆)
世界中で、多くの人が僕と同じように実感したんです。
いま、ビフォー・アフターの写真見せましたが、見せながらうれしいんですね。見てほしいんです。同様にSNSに世界中の人がビフォー・アフターの写真をアップしてる。みな感動して。
片づけができるようになると自己肯定感が上がるんです。僕も仕事はできるほうだったんですが、片づけが苦手で自己肯定感が低かった。だから自己肯定感を上げようと思ったら片づけをするのがいい。
人は変われるが、決意が必要。
決意だけでもだめ。覚悟しないといけない。決意をキープしなきゃいけない。「人生がときめく片づけの魔法」は、実は「片づけられる人間になれる方法」が書いてある本なんです。
そして読みながら覚悟をせまられ、決意をせまられる。読み終わった後、朝まで徹夜して片づけをした。そんなはがきが毎日のように届くんですね。
本は人の心を動かすエネルギーを持っている。
ベストセラーは口コミがすべて
ベストセラーといわれるものは口コミがすべてです。広告、テレビで取り上げられるということもあるが、どんなに取り上げられても口コミが起きない本はベストセラーにならない。
売れる本はその本を手に取った人が「これはよかったよ」と口コミで広めてくれる。広告以上の効果をみんながやってくれる。ロングセラーもすべて口コミです。
僕は音楽のエネルギー業者なんですと言った人がいた。つんくさん。ご存知ですよね。僕はつんくさんの本も作ったことあるんですが。
──音楽の神様がいて、僕は音楽の神様の下で働かせていただいているしもべなんです。音楽の持つエネルギーを扱っているエネルギー業者なんです。自分が作った音楽で明日も会社に行こうと思ったり失恋から立ち直ったり。そんな、人にプラスになるエネルギーを音楽にこめている。
僕は、本と同じだなと思った。読んだ人が元気になったり悩みが解決したり、自分の問題が解決したり、人生の問題が解決したりするんですよね。
僕のプロフィール
高校時代は硬式テニス部。へたでした。大学時代は演劇やってました。大学を卒業して、よく知らないままPHP研究所に入りました。ほかが全滅だったので。
入ってみたら「研究所」じゃなくて出版社だった。楽そうなイメージがあったんですね。9時5時で帰れるかなと。そうは問屋がおろさなかった。
最初は海外営業。大学時代はバックパッカーで放浪してたこともあった。仕事はちゃんとこなしていたが、当時の彼女が「私、銀行辞めて大学院行く」というので「僕も会社辞めて芝居やるよ」と退職届を出した。ところがなぜか僕をかわいがってくれてた「鬼の営業部長」が「君、辞めるのはいつでも辞められる。編集に向いてるかもしれないから、辞めるのはそれをやってからでもええんちゃうか」と。それで半年間だけやってみるかと、編集部に移った。その後、彼女との関係は「なんで辞めないの」と微妙になり、ふられた。だが、ふられたことで半年後には、いま辞めたら自分には何もなくなる、となったわけで、編集の仕事を続けることになった。ふってくれたおかげです。
その後サンマーク出版に移りました。新しい雑誌を作るということでその編集長にと、引き抜かれるようなかたちで転職しました。当時32歳くらい。ちょっと鼻が高かった。
ところが部下のマネジメントができない。部下に嫌われ、うつ病みたいになった。会社に行くのも部下の顔を見ることもいやになった。
副編集長に降格。雑誌は休刊になった。ン億円の赤字を出したんです。会社の利益を全部吹き飛ばしてしまうような。首になるかと思ったんですが、社長に「君、辞めるな」と言われて、残ることになった。それが、書籍の編集に移ることになった契機です。人生の大きな挫折だった。つらくてしかたなかった。でもあの挫折があったから、今は部下の気持ちも多少はわかるようになった。
最初にミリオンセラーをつくったのは今から20年前です。「病気にならない生き方」。140万部売れました。
毎年、新刊が何冊発売されるか知っていますか? 7万冊です。
年間7万冊も新刊が出てる。つまり、数万人の人が本を書いてるってことです。
本のプロフェッショナルと言われる人でも7万冊を全部知ってるわけではない。書店員さんでも自分の店にどんな本があるかということは検索しないとわからない。
年間総合ベストテンというのがあって、12月に発表される。年間の新刊が7万冊、それより前に出版された本も入るので20万冊くらいの中のベストテンということになります。この年間総合ベストテンに自分の作った本を入れるんだということを、十何年か命がけでやってきました。
サンマーク出版では2、3年に1回くらいはベストテンに入れてました。僕自身、自分がつくった本を4冊、ベストテンに入れてます。
ミリオンセラーとよばれるものをサンマークでは8冊出している。これはかなり多い。

いい話ばかり言いましたが…。
失敗から学ぶ
実は最初に作った本で大失敗している。2000年に書籍に移って初めてつくった本です。
初版2万部の本が返品率95%という、サンマーク出版始まって以来という数字を叩き出して、またやっちゃったかと。なんでこうなったか。
自分は原稿をリライト、磨き上げるのが得意だった。
磨き上げた原稿を、「脳内革命」の編集者であるサンマークでのボスに見せたら激賞された。社長からも。みんな「おもしろい」「ミリオンセラーになるかもしれん」と言った。 それで、有名な著者ではなかったのでふつうなら初版4000〜5000部というところを、2万部ということになったんです。
なぜ、売れなかったのか? 読者がいない本を作ってしまった。必要とする人がいなかった。中身を読めばいい本だと言ってくれる。でも、中を読むまでの動線ができていなかった。タイトルが失敗してるとか。いろんなことが失敗して。店で手に取ってもらえるための動線ができていなかった。
売れる本をつくっている編集者は何をしているのか? 彼らから学ばなければならない。
「人生は問いのレベルで決まる」という言葉を教えてくれた人がいます。表三郎さんという、駿台のカリスマ講師。僕は一時、“表信者”のひとりでした。心酔していました。
幸運なことに、僕は表さんの本を作ることができた。「答えが見つかるまで考え抜く技術」(サンマーク出版、2003年)です。 5万部くらい売れた。その本を作る過程でこの言葉を教えてくれた。
ノーベル賞を取るような人は、そういう問いを立てている。 なるほどと思った。自分は編集者として、問いを持たないといけないと思った。
たとえば「どうしたら幸せになれるか」。これには正解がない。著者なりに答えは書いてあっても。
「正解がない問い」は非常に大切。本は、その正解がない問いを与えてくれるんです。
読みながら考える。書いてあることを単なる情報として受け取るのでなく、読書しているとさまざまな雑念が浮かんできたり──その雑念そのものが僕は読書体験というものじゃないかと思うんですけど──いろんなことを考えながら一冊の本を読んでいく。いろんな問いが生まれるのがいい本じゃないのかと思う。
編集者とは何をしている人か

ひとことでいうと、ヒットをねらって本を作っています。こういうと、商業主義に走っているのかと言われるかもしれませんが、これは当然のことなんです。野球選手もヒットをねらう。いくらいいスイングをしてもヒットしないと意味がない。本がヒットしてこそ編集者。編集者は売れない本には興味がない。でも、売れる売れないは編集者によって基準が全然ちがう。ここにおもしろさがある。
本によってもイメージは違うと思いますが、僕の場合はビジネス本、自己啓発書、実用書を作っていたので、まず商品企画を立てる。
世の中に出ている本はすべて編集者が企画した本です。今はこういう時代だから、こういう答えを持っている人に、こういう人をターゲットに書いてもらえばいいのではないかと考える。目次も編集者が主に作っている。極端な場合「この一文から書き始めてください」と指示することもある。そうやって、一冊の本を、商品として恥ずかしくないものに仕上げていく、ディレクションしていくのが編集者の仕事です。
ライター(ブックライター)と一緒に取材して本を作っていくこともある。すぐれた経営者であっても本を書くのは得意でないこともある。本業が経営なのですから当然です。ダメ出しをする。書き足しもする。こんまりさんの原稿にも大量の赤字を入れてます。あたりまえです。こんまりさんの本業は「片づけ」ですから。
メディアへのプロデュース、文章は「てにをは」から、ミリ単位でデザインの訂正も指示する。本と著者をプロデュースする仕事です。
こんまりさんの世界的ヒットはどうして生まれたか
2010年4月10日。初めてこんまりさん(近藤麻理恵さん)と出会いました。
こんまりさんは5歳のときから雑誌「Esse」を読んでいたような人。高校生のとき「片づけ」に開眼。社会人になって2年、法人営業の仕事をしていたが退職して片づけの仕事を始めました。「自分の片づけは世界一」と確信をもって言う。小さいころから研究してきたという自信がみなぎっていた。当時25歳。彼女の本を出したいと思った。
彼女はお客さんから「本、出版しないんですか」と言われ、出版スクールに通い始めた。僕はその出版スクールに通っている人のプレゼンを審査する審査員として出会ったのです。3分間の彼女のスピーチを見てたら映像が浮かんだ。あ、この人はテレビに出る…。それくらい鮮烈だった。
「片づけはマインドが9割」「片づけはまつりなんです」「片づけには正しい順番があるんです」
おもしろいフレーズがぽんぽん出る。その仕事をひとすじにやってきた人だから出てくる言葉。僕は他の審査員に取られないように、その日、家に帰るなりすぐにパソコンを立ち上げ、こんまりさんにメールを打った。「僕と作れば30万部売れます」と。
若い人にメールでこんな風に部数を言ったのは最初で最後です。なぜか手が勝手に動いた。僕の直感です。オーラと言ってもいいかもしれない。
そんな連絡をしたのは僕だけではなかった。でも、結局、僕が一番最初に彼女に会いました。今度は僕が審査される番(笑)
そして、こんまりさんから「サンマーク出版と高橋さんにときめきました」とメールが来ました。
4月30日。最初の打ち合わせ。「どんな本にしたい?」と聞くと即答された。「売れる本を」と。
僕は「読者を限定しないほうがいい」と提案した。こんまりさんは当時「乙女の整理収納レッスン」というブログをやってたんですが、老若男女、本をふだん読まない人も読んでくれないとだめだと。ある一定の世代に共感されるような本ではだめだと。
イラストや写真は一切入れないことにした。特に、イラストには好みがある。わかりやすくなるかもしれないけど、限定されてしまう、と。それでもいいか?と聞くと「売れるならなんでもいいです」と。
サンプル原稿が送られてきたが、セミナーのレジュメみたいな、説明書みたいなものだった。本になっていない。エネルギーがこもっていない。ただ説明しただけだと読む人の心をふるわせることはできない。
僕は自分が作った本を2冊渡し、これで学んでくれ、2つをミックスした文体で書いてくれと言いました。こんまりさんが失敗した片づけのヒストリーを書いてくれ、と。10代のころからいろいろチャレンジして研究してきた、そのプロセスこそがおもしろいんだと。読者はまだ片づけられない人だから、失敗した話に共感を持つ。そこがおもしろいのだと。
その後、割と放置しました。
こんまりさんからSOSのメールがきた。「書けないんです」「もっとかまってください」
そこから週2回くらい締め切りを作った。ほぼ毎日電話とメール。週1回は会ってた。
天河神社(奈良県)に祈願に行ったりもした。
当時、トライアスリートの本を作ったことがきっかけでトライアスロンに挑戦することになった。スイムは1.5km。それまで200m泳いだことしかなかったのに。で、2ヶ月、集中トレーニングして、トライアスロン完走しました。走りながら願掛けをした。30万部売れるよう…。
あるとき、こんまりさんから届いた原稿を読みながらじーんときた瞬間があった。「片づけの原稿で46歳のおっさんのおれが、なんで電車の中で涙を流しそうになってるんだ」(笑)
これはもしかしたらすごいことになるかもしれない、30万部ではなく100万部めざすべきかもしれないと思うようになった。
2010年12月。著者完成稿が届いた。そこから大幅な直しを入れた。
2010年12月。「王様のブランチ」に取り上げられることになった。本は翌年1月に出すことになっていたが、それで前倒しすることになった。2010年12月発売。飛ぶように売れていった。
こんまりさんはその年のはじめ、目標として「王様のブランチに出る」と書いていた。そして実際に出た。これってすごいと思いませんか。そういう人たちって、やっぱり、そういうものを持ってるんですね。頭の中に描いて、それを実現していく。
夢を叶えるための方法の一つが「紙に書く」。それが実現したんです。
2011年3月。東日本大震災。本の売れ行きはいったん止まった。広告も打てなくなった。このとき11万部くらい。
2011年6月。「キンスマ」のディレクターから「出演決まりました。キンスマに出てください」と連絡があった。実際にはその後予定が延びて、9月に出演となった。そのときは30万部くらい。一見売れているようだが、在庫をかかえていてリスクがある状態だった。ちょうど放送の日に100万部突破。その後、信じられない勢いで伸びた。日本で売れたのはキンスマの影響が大きいです。
世界的ベストセラーに
従来、日本の本は台湾、中国や韓国では売られるけど欧米ではあまり出版されなかった。こんまりさんは、この壁を打ち破った。
2012年12月、ドイツの出版社と契約。
3月10日。僕は「アメリカでミリオンセラーにする」と紙に書いた。こんまりさんが「王様のブランチに出る」と書いたように。
英語版のカタログを作った。ニューヨークのエージェントに声をかけた。翻訳原稿を渡した。
4月から僕は英語でスピーチをするということを考え、英語の勉強を始めた。一時は狂ったように1日3時間、寸暇を惜しんで勉強した。なんのために? 願掛けの一種かもしれない。そうすることで、勉強すればするほど、目標に近づけるかのように。
2014年4月、こんまりさん結婚。僕は披露宴でスピーチした。「こんまりさんは世界のこんまりさんになる!」と。
2014年8月、イギリスで出版。
2014年11月、アメリカで出版。
ニューヨークタイムズから取材がきた。記者は本を読んで感動した「こんまり信者」だった。とても熱のこもった記事を書いてくれた。あっという間にベストセラーになった。この記者は知り合いに本をすすめ、「マンション1棟に買わせた」そうだ。やっぱり口コミがすべてなんです。
その後、「TIME」の「最も影響力のある100人」2015年版artist部門で選出された。日本人で載ったのはこんまりさんと村上春樹だった。
安岡正篤(やすおかまさひろ)さんの言葉に「有名無力、無名有力」がある。無名でもすばらしい人たちがたくさんいる。そういう人を発掘して本を作りたい。
こんまりさんに「本を出して、何を実現したいの?」と聞いた時、こんまりさんは「私、世界中を片づけたいんです」と即答した。まだ原稿を数行しか書いてなかった頃に。でも、言葉は本物だった。
H 華がある人
U 運がいい人
K 言葉を持っている人
こういう人がいい本を書く。HUK。これが大事。でも、これは表のHUK。実は裏のHUKがある(爆笑)
H ヘンタイ
U 売れたい
K 狂ってる
こんまりさん、狂ってました。(笑)
本を読もう!
本は(著者の)頭の中にあるもの。口にして、言葉にして、文章になると違ってくる。「見える化」される。はじめて自分が何を考えているかわかる。
「本」という漢字が僕は大好きです。「本」は本物、本業、本体、本気…「日本」にも使われている。大事なことを、日本人は「本」の字に託してきた。
読書は食事と同じです。何を食べたかは忘れても、体の栄養分になっている。食べたもので体はできている。読み物と同じ。いいものを読むと心が潤う。誹謗中傷やゴシップばかりでは心は、すさんでいく。
今はたくさんの文字があふれかえっている。文字を読む量でいうと、僕たちは10年前、20年前と比べて圧倒的に、知らない間に読んでいる。そのほとんどがスマホです。
でも、読み物はまちがいなく影響します。ほんのわずかな時間でも「本」に変えたら、プラスになる。
僕の場合、人生で大事なことはすべて、本と著者が教えてくれました。
言葉というのは世界の解像度をあげる力を持っている。見えている世界が変わってくるんです。
本という商品は言葉で作られている。
本は雷です。本を読んで、一撃で人生が変わることがある。
本は手紙である。ただし、宛名のない手紙である。誰かわからない人に向けて書かれている。
本は国境も時代も越える。まったく予想もしなかった人が自分の書いた本を読んでくれる。
今あまり本を読んでないという人もいらっしゃると思います。今日のこの話をきっかけに、本を読む時間をとってみてください…これは自分にも向けて。僕もスマホ見てる時間、めちゃくちゃ長いので(笑)。

《講演を終えて》
「僕は高校時代は目立たない生徒でした。今日のように同窓会の総会で話をするようになるとは思ってもみなかった。あのころの自分に教えてやりたいです」と、高橋さん。素敵なお話をありがとうございました。
(2025.8.31)